『上海ノース・ステーション』立ち読み
 本ページで『上海ノース・ステーション』の一部を立ち読みいただくことができます。
本ページで『上海ノース・ステーション』の一部を立ち読みいただくことができます。全文は電子書籍(Kindle版)または単行本でお読みいただけます。電子書籍は下記のリンクからアマゾンにてご購入ください(Kindle unlimitedで無料で読むこともできます)。 単行本については、本作は『小説集カレンシー・レボリューション』に収録されていますので、下記のリンクよりアマゾンにてお求めください(『小説集カレンシー・レボリューション』には関連した長編小説1本、中編小説1本と合わせて合計3本の作品が収録されています)。
|
「動きがあったのか」
「はい。宋子文は今夜の汽車で南京を発ち明日の朝上海に着きます」
「いつもは木曜日か金曜日に南京をでるはずだが、繰り上がるということだな」
「青島にいる母親が危篤だそうで、上海での仕事を済ませてすぐに青島に向かうために急遽今日の上海行きに乗ることになったようです」
「暗殺は明日の朝実行されるのか」
「はい。そのようです」
田中は蘇州河のほうに顔を向けた。自分の考えた計画がいよいよ明日実行されると思い、思わず頬がほころぶのをみられたくなかったのだ。目の前を小さな貨物船が雨と風に逆らって遡っていく。田中はその船をみながら、許清からみえないほうの口元を歪めた。
許清は田中の横顔に訊いた。
「どうしますか。諦めますか」
「なぜ諦めなくてはならない」
「重光が上海行きの列車に乗るのは明日か明後日でしょう。重光と宋子文が同じ汽車から降りてくるところを襲撃しなくてはならないのですよね」
「問題はないさ。宋子文が重光よりもあとに南京発の列車に乗る予定に変わったというのならばこの計画は中止しなくてはならないだろうが、その逆で、宋子文が重光より早く列車に乗ることとなったのならば問題ない。重光が列車に乗る日程を繰り上げさせることは簡単だ。予め方法は考えてある」
「どうするのですか」
田中は許清のほうに向きなおった。
「抗日組織のふりをして、上海の領事館に爆弾を仕掛けた、と脅迫状を送りつける。爆弾騒ぎは日常茶飯事だが、明日に南京で重要な会議の予定でもない限り、多少なりとも責任感があれば重光は陣頭指揮のために上海に戻ってくるはずだ」
「なるほど。しかしどうですかね。わざわざ爆破される危険のあるところに帰ってきますかね。まともな人間なら、仮に上海に戻る予定でも戻るのをやめて安全な南京に残ろうとするのではないですか」
「まともじゃない人間には、まともな人間の行動はわからんのだな」
田中は許清を薄目でみた。許清は懐中時計を取りだしていった。
「しかしもう四時です。脅迫状を領事館の郵便受けに入れても、領事館のひとは今日中にはみないんじゃありませんか」
「律儀に郵便受けに入れる必要などない。上海の武官室にそういう脅迫状が届いたといって、おれから直接重光に連絡をする。念のため『代理公使はすぐに上海に戻るべきだ』とつけ加える。ともかくおれに任せておけ。明日の朝、重光は宋子文とともに列車から降りてくる。おまえはそこを襲う。重光殺害に成功すれば六千だ」
全文は 【単行本】小説集カレンシー・レボリューション でお読みいただけます。 |
田中はそういって再び蘇州河のほうを向き、顔の右側に右手を当て、許清から顔がみえないようにして微笑んだ。そして、
「こいつはうまくいく。新たな歴史が始まる」
とつぶやいた。
その声は雨が傘に当たる音にかき消されて、おそらく許清の耳には聞こえていない。
燕克治は、南京の財政部に近い宿の部屋で窓辺に椅子を寄せ、窓枠に肘を置いてそとをみている。昼から降り始めた雨が降り続いている。窓のすぐ下の大通りには、ときおり車が水しぶきをあげて通り過ぎるだけで、歩くものはほとんどいない。
克治は考えている。
昼過ぎに顧麗玉(グーリーユー)が訪ねてきた。宋子文が今日の夜行列車で上海に向かうと伝えにきたのだ。顧麗玉の話は朱偉とともに聞いた。
そのあとすぐに上海へ電報を打つために朱偉を宿に残して電報局に向かった。が、多少慌てていたのか、電報局への途上で財布を持たずにでてきたことに気づき、宿へ戻ってみると朱偉は外出していた。克治が宿をでてから戻るまで十五分しか経っていない。朱偉は克治が宿をでるとすぐにでかけたようだ。
そのときはなんとも思わなかったが、電報を打ち終わり宿へ戻っても朱偉は戻っておらず、夕食時になっても戻らなかった。なにやら違和感があった。朱偉は、一週間前の河畔の飯館での夕食以降、常に克治と行動をともにしている。つまり宋子文の予定は顧麗玉から情報を得ることになっていると知ったときから克治のそばを離れなくなった。ところが顧麗玉が情報をもたらすと途端にいなくなった。怪しむのが道理であろう。
思えば、最初に朱偉の行動に違和感をもったのは河岸で夕食をともにしたときだった。克治はあの夜のことを順を追って思いだしてみた。
(そういえば、妙なことをいっていた)
飯館で朱偉が唐突に重光葵の名を口にしたことを思いだしたのだ。あのとき克治は重光のことを知らなかった。そのため朱偉が話題を変えると重光の名は克治の意識から消え去った。しかし改めて考えてみれば気にかかる。なぜ突然重光の名を口にしたのか。
重光について調べればなにかわかるかもしれないが、果たしてどうやって調べるのか。新聞で調べれば最近の行動や今後の予定がある程度わかるかもしれない。しかしそれでは時間がかかる。手っ取り早いのは事情に通じている日本人に訊いてみることだが、日本人に知り合いなどいない。
(いや、待てよ。いる。あの男だ)
廬山での蒋介石暗殺未遂の際の逃亡に手を貸してくれた男。あれは日本人の新聞記者だった。
(なにはともあれ、会ってみるか)
克治はサイドボードのうえに無造作に置かれた名刺を手に取った。
全文は 【単行本】小説集カレンシー・レボリューション でお読みいただけます。 |
名刺のうえに手書きされた住所を訪ねていくと、小島譲次は南京にいるものの、いまは外出しているとのことだった。
宿のロビーで焦れながら、いつ戻るかわからぬ相手を待っていると、幸いにも一時間ほどでアルコールで微かに頬を赤らめた小島が現れた。
小島はすぐに克治に気づき、古い友人にあったかのように嬉しそうな顔をして、克治の右手を握った。
「まさか、もうやったのか」
小島のいう「やったのか」の目的語はむろん蒋介石である。
「いや、そうではない。今日は教えてもらいたいことがあってきた」
部屋にはいると小島は、廬山のときと同じようにブランデーをグラスに注いで克治の前に置いた。
克治は「謝謝(シエシエ)」といっただけでグラスには手をのばさずに訊いた。
「重光葵について訊きたいのだが」
「重光葵?日本代理公使のことか」
「そうだ」
小島は怪訝そうに首を傾げた。
「蒋介石を狙うきみがなぜ日本の公使のことを訊く」
克治はことばを返すのを躊躇した。不審な動きをしている舎弟がその名をふと口にしたことが気になっているのだが、なぜそれが気になるのかは、背景にある事情を話さなければ理解されないだろう。
ただ、目の前の男は自分が暗殺者であることを知っているのであり、ある程度のことは話してしまっても構わないだろう、と考えなおした。
「われわれの組織はいま蒋介石ではない新たな対象を狙っている。私は舎弟とともにその対象のことを調べていたんだが、その舎弟が突如いなくなったんだ。それまでずっとそばにいたやつが急に消えたんで気になって考えたんだが、少し前にあいつが唐突に重光の名を口にしたことを思いだした。あいつと重光の関係に全く思い当たるところがなくて、きみに重光のことを訊けばなにかわかるのではないかと思い、ここにきた」
「なぞかけのようだな。情報が少なすぎるぞ」小島は首を傾げながら自分のグラスを口に運んだ。「どういう状況で代理公使の名がでたんだ」
「特になんの脈略もなかったと思う。あいつに夕食に誘われて、飯館で顔を合わせたら急に『重光を知っているか』と訊かれた」
「わからんな」
全文は 【単行本】小説集カレンシー・レボリューション でお読みいただけます。 |
 未来技術奇譚集 素顔のままで
未来技術奇譚集 素顔のままで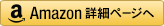
 小説集 カレンシー・レボリューション
小説集 カレンシー・レボリューション 朱紈
朱紈 上海エイレーネー
上海エイレーネー カレンシー・ウォー 小説・日中通貨戦争
カレンシー・ウォー 小説・日中通貨戦争